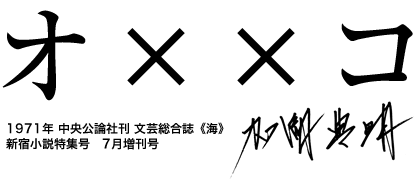
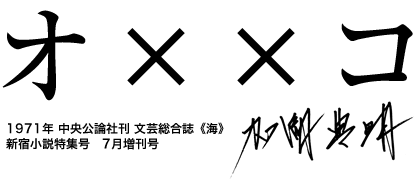
「馬鹿野郎」強い日差しが、看護人のかぶっている制帽のつばさが、そいつの目を、全く影にしていた。看護人は何も答えない。彼女は歩き出した。自分の背中の建物がだんだん小さくなって行くのを感じていた。自分を閉じ籠めていた、安手のフィルターのような意味しか持たないその建物が。乾燥したジャリ道は、時の進むのをひどく遅く感じさせていた。そよぐと云うにはおよそほど遠い風が、彼女の輪郭を形作って、体の前から後へ吹いていた。久しぶりにこんなに歩いて、体に血が充分回り、さえない気分とは裏腹に、もう一つの何かは、やや生気を持ち始めていた。その回り出した血が左手首の所で、時々わだかまりを、示している。いってみりゃ、それは私の歴史さ。この左手首の五本の傷は、私が自分で作って来た、私だけの傷さ。私が生きていることを、そう簡単には他人に手渡せないという証しなのさ。この五本の傷が、五回も この埃っぽい道を歩かせているのさ。後に小さくなっていく建物も、私には、五回とも同じ色だった。私自身も変色はしなかった。所詮、あんな建物に私の中身の色なんか見えやしないのさ。私は、この傷を、俗にいう自殺とかいう奴のために描いているんじゃないんだ。なぜ皆んなは、私が手首に線を引くと、自殺だなんだと騒ぐのだろう。第一自殺ってやつを私は信じない。あれは、殺されているんだ。本当は他殺なんだ、あれは。自殺自殺とよくあるけど、あれは皆んな周りに殺されているんだ。人の気持ちなんてのはそんなんじゃないんだ。だのに、私が線を引くと、それは、自殺だ、ナミじゃないと、私を、あの黄色いフィルターに閉じ込める。ジャリ道の踏み心地は、相変らず不安定で、体中にまわった 血も少し疲れ始めていた。彼女が歩いている砂利道と丁度T字形に、コンクリートの道が走っていた。彼女には、それが白い線のように、それも少しゆらゆら揺れて映っていた。あそこまで行けば、バスか何かあるはずであった。「ガシャーン」鼓膜の振動には限界のような、文字通りの大音響が彼女を襲った。瞬間的の彼女は身を小さくした。何かキラキラ光る物が、無数に眼前を横切る。それが過ぎると、辺りは灰色の濛々とした煙とも埃ともつかない輪郭のない景色になっていた。額のあたりが引き吊るのを憶える。その煙とともに、一瞬、時間が止ったような静かさが続いた。煙が晴れて来る。煙の中が少しずつはっきりして来る。三台の車が闘牛士と牛がクロスした次の瞬間を把えた写真のように、全く静止した状態に、それぞれ勝手な方向に、半分ぐら いの意思を持った形で止っている。一台を省いて後の二台は道路の上にはなかった。その道の外に横倒しになった小型トラックから、妙にユーモラスな唸り声がする。豚が、胴をほとんど半分位ちぎれかかって、泡とも血ともつかない体汁を体の三倍位の面積の出して、その浅いプールみたいな物を大まかな動作のけいれんでいっそうかき廻し、たれ流している糞尿とともに、色彩の鮮やかさとは別に、強い臭気を発していた。もう一台の、道から外れた車は、全く静かで、フロントグラスに人の頭位の丸い穴がすっぽり抜けて、その丸の周りがきれいに赤鉛筆で丸を画いたように赤くなっていた。ようやく彼女は立ち上り、自分をどうしようかとコントロールし始めた時、かろうじて道の中に止っているプラモデル のような形の車のドアが開いた。男は、車から下りると、フロントグラスに穴の開いた車に正確に歩いて行き、車には触れずに覗き込む。無表情。ほんの十秒も車の中を見ていただろうか。男は、横倒しになった小型トラックの、彼女から死角になっている所へ行って、また十秒位過ぎた。そのトラックをひと廻りすると、男は、車から降りる前から決っていたように、彼女に向って歩いて来る。淀んだ空気以外は、その男と彼女だけがあるのみだった。歩いて来る男は、ヤクザ映画のスターみたいな歩き方で、まだ若そうなのに、自分の生き方の全てが決定しているような風だった。「どこまで行くの…」「新宿」「乗って行くかい」彼女はだまっている。男は、暫く、そうしている彼女の目を中心に体中を非常なスピードで、まるで物を見るようになめまわす。そして、男は視線を彼女の目に戻し、差し込むような眼差しを送ると、クルッと向きをかえ自分の車の方へ歩き出していた。車は東京に向かって、高速道路をかなりのスピードで走っている。むし暑かった。空は暗く、直線的な道と、空から押し下って来る黒い雲で、車の行く先を全く焦点のない行先に見せている。男は二十二歳ぐらい。学生ともそうでないともいえるような風体だった。髪は短めの長髪で、色はその浅黒さの割に中身から来た黒さではない。余りにプラスティックな黒さである。乗って五分もしない内に、男はなり恰好とは 裏腹な、妙に軽薄な、何んの基準も持っていないなれなれしさを見せ始めていた。「新宿へ、何をしに行くの」男が聞く。「帰るんだよ」「こっちには、何しに来てたの」「髪の毛を、洗いに来てたんだ」「へえー」暗い空は、こらえ切れずに大粒の雨を降らせ始めていた。男「新宿は、どのへん」彼女「ゴールデン横丁」
いつの間にか、男の手が、変速レバーから、彼女の右手をつかんでいた。汗ばんで熱い手だった。「始めやがったな。このプラスティック黒め」と彼女は、内心思いつつ、久しぶりのこういった状態に、まんざら悪い気持ちもしなかった。相手なんかはどうでもよかったのだ。男は、自分の左手で、彼女の手を、自分の股に置いて、上から彼女の手を、さするようにしていた。時どき、彼女が、手に力を入れてやると、男は、その度に、彼女を視る。長いこと我慢していたのだろう、男は、唐突に、彼女の手を、ズボンの中にめり込ませる。
 細過ぎるズボンに、強引に、変な体形で、やるものだから、彼女は、少し声を上げる。男はまた彼女を視る。彼女は、自分で、男のベルトと、チャックを外してやる。そして、勢いよく腕を突込んでやる。中は、まるで、湿った温室のようだった。陰毛が汗に濡れているのを感じながら、彼女の手は、いきなり、男のモノをつかんだ。男が「うッ」と、発して、一瞬身を引きつらせる。静かに、彼女は、はじめてやった。男は、包茎だった。その皮を、むいて、しっかり手の中に入れ、まるでポンプのように、力を入れたり、ぬいたりした。男には、車をドライブしているのと、もう一つの自分の現実との、境いがつかなくなって来ていた。男が、潤んで「くわえてくれ」彼女は、黙って、シートを後へずらした男の股へ、口を突込んでいった。口の中で男はますます緊張して、微妙に震えている。その大きさは、その男の限界まで来ていた。彼女のつばと、男の体液で、口の中は、高 熱の溶解と化していた。時どき、男が、片手で彼女の頭を、自分の中心に向けて押しつける。男の中の男は、喉チンコを通りこして、彼女の首の中程までささっている。「こんなに入れる女は、お前がはじめてだ」彼女続ける。「いいぞ」「ああ」「ううッ」男が唸り出す。男ってのは、調子が出るとすぐしゃべり出す。こいつに私は、いつも白けさせられるんだ。と、突然、喉の中心まで入っていた亀頭が、最後の拡張を図る。「ぐう…」男は、空を突くような声を出す。彼女は男のこの最後の声が、なんとも好きだ。堪えることなんか少しも出来ないのに、必死で、こらえようとするこの瞬間を、彼女は、充分味わった。射精が始まった。彼女は、男の呼吸に合わせて、ぐいぐい飲み込む。彼女の喉は、熱地の如くとなっていった。男は、このまま車を運転しているのが、ひどくおっくうに見える。「止めようか」「いや走らせて」車の外は、今や、雨が槍のように、くるまに突きささり、跳ね返っていく。二人の熱気と、外の雨で、フロントグラスの三分の一位しか外は、判別出来ない。男のモノは、行ってもまだ、リンとして立ったままである。彼女は、男の熱液を、全部吸い取ると、自分のシートから男の正面に向って、しゃがみ 込むように男の上に座り込んだ。そうして、自分で、立っている男のモノを、自分の湿りに湿った中心に、さし入れた。彼女はパンティとか、パンティストッキングとかを、はいた事はなかった。ミニをはこうが、ズボンをはこうが、下に、なにかをつけるのは嫌だった。男は、女の重みと、あい変わらずの戦慄を続ける自分の中心の感度で、ただ、道路が、直線でいてくれと願っていた。彼女は、りんりつしている男を、自分の体のなるべく奥深く、入るように、数回体を前後に、ねじり、位置を定めると、静かに、深く、ゆるやかな動きを、腰に与えていった。ああ、体が登っていく。体の関節が、しっかりと、力をはらんで、決められたように、よさが、やってくる。男の陰毛に、自分のクリトリスが、非常な 速さをもっていどんでいる。ささっている男と、自分のクリトリスのよさの反復は、限界まで来た。「ああまただ」彼女は、メラメラと、自分のイメージの、輪郭が、はっきりしだした。「ああ、まただ」「また自分だ」「ああ、また駄目だ」彼女は、完全にアクメに達している体とは、全く分離して、アクメの瞬間に涌いてくる自分だけのイメージ。なぜ私は、体のジョイントしか出来ないのだろう。やる事は、本当は私は、私自身をなくするために―その時ぐらい―私自身をなくするために、やりたいんだ。急速に、血が下がっていくのを憶えた。下半身の湿りが、ただの冷たさに、変わっていく。男から離れて、彼女は、体とは別に、ひどく憂鬱な、脳が、けいれんするような気分を、隠す事が、出来ないでい た。男も彼女も無言のまま、車は、プールのような水面を、しぶきを上げて走っていた。「また、会おうか」彼女は男の顔を見返す。「名前いえよ」また見返す。「なにやってるの」「どこに住んでるの」男の軽薄さは一言しゃべる度につのり、彼女はますますブルーになっていく。なぜ、この手のこういったプラモデルみたいな車に乗った一見学生風の体ばかり立派な男ってのは、話せば話す程その人の輪郭を失くして行くのだろう。人が多過ぎるな。どうしてこう並ばかりの男が多くて、いっぱしの男ってのがいないのかなあ。まあ、でもこの男、私を黄色いフィルターから現実へ帰って来る切符の役目を果たしてくれたんだ。車は、伊勢丹を過ぎ区役所通りに入っていた。「ここでいいわ」男は、まだしつこく彼女との次のコンタクトを持ちたがって口と表情を動かしていた。高速道路から降り 続いている雨は、新宿の町もべっとりと濡らしていた。町の活気が降る雨をどんどん蒸気にしてしまい、それが町のたたずまいをひどくむし暑くさせていた。彼女は、とりわけ新宿でなければとか、特別、新宿が好きだという主体を持った理由があった訳ではない。要するに、何となくというのが一番の理由であった。それと、三度目から五度目の時まで、完全とはいいがたい、いわば移動同棲のような形で、彼女に最も理解を持っている学生が住んでいるからでもあった。今も彼の住んでいた汚いバーの二階の三帖ぐらいの巣へ、自然に彼女は歩いていた。ゴールデン横丁へ入ると昔の都電のレールを、大きな木の杭で塞いで、道を作っている所がある。そこまで来た時、彼女の目に一人の乞食が映った。乞食は、 年なんぞはまるっきり解らず、ただその太い木の杭にもたれかかり、坐っているだけだった。丁度彼女が乞食の前を通り過ぎる時、男とも女ともつかないその乞食と視線が合った。しかし、乞食はそのまま、彼女を通した遠くを視る目に変わっていた。彼女は歩く。こんな雨の中、なんであんな所に坐ってるんだろう。それっきりその乞食の事は忘れてしまった。その学生が住んでいる二階へ行くのには、一階の六坪ぐらいのバーの中を通らなければならない。そのバーは、ほとんどがライターとか放送関係とか、いわゆる日本の皮層文化をささえている人種が主な客であった。店にはまだ客はいなかった。ママ一人のこの店は、満員という事がなかった。ママは、突然現れた彼女に驚いた。「彼は?」「あの人今、捕まってんのよ」このママと彼は、彼女が同棲を始める前から、二階の二部屋で互いに行ったり来たりしていたらしい。しかし、彼女にはそんな事は、全然気にならなかった。「ああそう、またはいってんの」「今度は、随分長いのよ」酔うと、その昔中国で転々と渡り歩いて来たという話や、歌がただ一つの出し物のママは、少し淋しさを示した。「二階、開いてる」「ああ、開いてるよ」部屋は、カビ臭さと独り者の男の散らかし方で散乱としていた。長い事人が入った事がないとみえて部屋の中の空気は、今まで彼女が 歩いて来た空気と違う冷たさを持っていた。彼女は、敷っぱなしのカビ臭い蒲団にもぐり込むと、そのまま眠ってしまった。動きらしい動きもしないまま、二日も寝ていたろうか。体の神経がほとんど麻痺する位、体がゆるんでいた。そうした三日目の朝、彼は帰って来た。真暗な部屋の入口を、ガタンと音をさせたかと思うと、見覚えのある体が入って来た。彼は、部屋の中で一瞬戸惑いをみせたが、すぐ彼女を判別すると「なんだ、お前、帰ってたのか」。彼女は返事もせず、彼の動作を、もう一人の人間と自分が交す新しい空気の淀みを味わっていた。「今度は、やられたよ」「警察ってのは、病人を作る工場みてえだな」「今度ばかりは自分ってものを君じゃないけど考えさせられたよ」なんだか訳の解らな い事を、咳きながら、彼女が寝ている正反対の部屋の隅へ行って坐り込んだ。すぐにゴソゴソ這って来て、「タバコ、あるか」彼女、自分のバックを少し動かしてやる。タバコを取り出すと、また部屋のすみへ這って行って坐り込む。マッチの音がして、彼の顔が暗い中に浮び上がる。疲れているはずなのに、髭も伸びないで意外にシャンとした顔をしている。「きれいな顔してんのね」「警察も、最近は、出す時にゃちゃんと化粧させるんだ。ぶん殴った分だけ厚化粧させられるのさ」この小さなセクトを持っている学生は、その何十回目かの投獄の疲れの割には、自分の部屋に自分の女が待っていたという事で、単純に動物的な温かみを感じ、活発にしゃべり続けた。「今度は、黄色いフィルター早かったじゃないか」「向こうもこっちもなれあいさ、狂ってる事をお互いゲームにしちまってるのさ」「体は、元通りになってんのか」「うん、男と寝る事出来るよ」「奴等はよ、話で通じさせようとしないんだ。こっちの事、ガキの病気かママゴト位にしか考えていないんだ。奴等の話の原点は、結局暴力なんだ、人間の最も単純な所からの、発想なんだ。あいつらの錯覚ったらないぜ。それに、あいつ等の顔ときたら、ほとんど、パッケージに近いんだ。だから、話なんてものにまるでならない。猿同士が金使って、漫才やってるようなものだ」「私の方も、黄色い漫才ごっこだよ。ちょっと飽きて来たけどね」「お前はまとも、過ぎるんだよ。自分自身にさあ」「あんただってまともだよ。それも男の過剰なエネルギーって奴でさあ。人の事なんか放っとく方がいいよ」話が止切れて数分たった。「私、オナカすいたよ」「そうだな」入って来た時と同じ音をさせて彼は出て行った。どうやら、隣のママの部屋へ行ってるらしい。二言、三言、話し声がしてママの声とも、何んともつかないしゃべり声がする。「電気つけるぞ」入って来るなりそう言って、片手で天井のスイッチをひねる。もう片方の腕から、何やら音を立てて落ちる。「ああしまった!」明るくなった電灯の下で、丼から半分位こぼれかかった五目メシみたいなものがころがっていた。窓らしい窓のない部屋だから、昼でもアンダーな部屋の明るさがようやく適正になる。彼女もようやく起き上がり、二人でそのメシをモソモソ食べ出した。冷えて口にまずかったが、二 人には、久しぶりのメシらしいメシであった。食べ終って、彼はタバコを歯でくわえ、六十Wの電球を見つめ、くわえタバコを、親指と人差し指で根元から先へとしごいていた。その動作を彼女、三十分近くも見つめていた。小さな牢屋のような部屋の中は、二人の発するアクでほとんど完全な密室と化していた。
細過ぎるズボンに、強引に、変な体形で、やるものだから、彼女は、少し声を上げる。男はまた彼女を視る。彼女は、自分で、男のベルトと、チャックを外してやる。そして、勢いよく腕を突込んでやる。中は、まるで、湿った温室のようだった。陰毛が汗に濡れているのを感じながら、彼女の手は、いきなり、男のモノをつかんだ。男が「うッ」と、発して、一瞬身を引きつらせる。静かに、彼女は、はじめてやった。男は、包茎だった。その皮を、むいて、しっかり手の中に入れ、まるでポンプのように、力を入れたり、ぬいたりした。男には、車をドライブしているのと、もう一つの自分の現実との、境いがつかなくなって来ていた。男が、潤んで「くわえてくれ」彼女は、黙って、シートを後へずらした男の股へ、口を突込んでいった。口の中で男はますます緊張して、微妙に震えている。その大きさは、その男の限界まで来ていた。彼女のつばと、男の体液で、口の中は、高 熱の溶解と化していた。時どき、男が、片手で彼女の頭を、自分の中心に向けて押しつける。男の中の男は、喉チンコを通りこして、彼女の首の中程までささっている。「こんなに入れる女は、お前がはじめてだ」彼女続ける。「いいぞ」「ああ」「ううッ」男が唸り出す。男ってのは、調子が出るとすぐしゃべり出す。こいつに私は、いつも白けさせられるんだ。と、突然、喉の中心まで入っていた亀頭が、最後の拡張を図る。「ぐう…」男は、空を突くような声を出す。彼女は男のこの最後の声が、なんとも好きだ。堪えることなんか少しも出来ないのに、必死で、こらえようとするこの瞬間を、彼女は、充分味わった。射精が始まった。彼女は、男の呼吸に合わせて、ぐいぐい飲み込む。彼女の喉は、熱地の如くとなっていった。男は、このまま車を運転しているのが、ひどくおっくうに見える。「止めようか」「いや走らせて」車の外は、今や、雨が槍のように、くるまに突きささり、跳ね返っていく。二人の熱気と、外の雨で、フロントグラスの三分の一位しか外は、判別出来ない。男のモノは、行ってもまだ、リンとして立ったままである。彼女は、男の熱液を、全部吸い取ると、自分のシートから男の正面に向って、しゃがみ 込むように男の上に座り込んだ。そうして、自分で、立っている男のモノを、自分の湿りに湿った中心に、さし入れた。彼女はパンティとか、パンティストッキングとかを、はいた事はなかった。ミニをはこうが、ズボンをはこうが、下に、なにかをつけるのは嫌だった。男は、女の重みと、あい変わらずの戦慄を続ける自分の中心の感度で、ただ、道路が、直線でいてくれと願っていた。彼女は、りんりつしている男を、自分の体のなるべく奥深く、入るように、数回体を前後に、ねじり、位置を定めると、静かに、深く、ゆるやかな動きを、腰に与えていった。ああ、体が登っていく。体の関節が、しっかりと、力をはらんで、決められたように、よさが、やってくる。男の陰毛に、自分のクリトリスが、非常な 速さをもっていどんでいる。ささっている男と、自分のクリトリスのよさの反復は、限界まで来た。「ああまただ」彼女は、メラメラと、自分のイメージの、輪郭が、はっきりしだした。「ああ、まただ」「また自分だ」「ああ、また駄目だ」彼女は、完全にアクメに達している体とは、全く分離して、アクメの瞬間に涌いてくる自分だけのイメージ。なぜ私は、体のジョイントしか出来ないのだろう。やる事は、本当は私は、私自身をなくするために―その時ぐらい―私自身をなくするために、やりたいんだ。急速に、血が下がっていくのを憶えた。下半身の湿りが、ただの冷たさに、変わっていく。男から離れて、彼女は、体とは別に、ひどく憂鬱な、脳が、けいれんするような気分を、隠す事が、出来ないでい た。男も彼女も無言のまま、車は、プールのような水面を、しぶきを上げて走っていた。「また、会おうか」彼女は男の顔を見返す。「名前いえよ」また見返す。「なにやってるの」「どこに住んでるの」男の軽薄さは一言しゃべる度につのり、彼女はますますブルーになっていく。なぜ、この手のこういったプラモデルみたいな車に乗った一見学生風の体ばかり立派な男ってのは、話せば話す程その人の輪郭を失くして行くのだろう。人が多過ぎるな。どうしてこう並ばかりの男が多くて、いっぱしの男ってのがいないのかなあ。まあ、でもこの男、私を黄色いフィルターから現実へ帰って来る切符の役目を果たしてくれたんだ。車は、伊勢丹を過ぎ区役所通りに入っていた。「ここでいいわ」男は、まだしつこく彼女との次のコンタクトを持ちたがって口と表情を動かしていた。高速道路から降り 続いている雨は、新宿の町もべっとりと濡らしていた。町の活気が降る雨をどんどん蒸気にしてしまい、それが町のたたずまいをひどくむし暑くさせていた。彼女は、とりわけ新宿でなければとか、特別、新宿が好きだという主体を持った理由があった訳ではない。要するに、何となくというのが一番の理由であった。それと、三度目から五度目の時まで、完全とはいいがたい、いわば移動同棲のような形で、彼女に最も理解を持っている学生が住んでいるからでもあった。今も彼の住んでいた汚いバーの二階の三帖ぐらいの巣へ、自然に彼女は歩いていた。ゴールデン横丁へ入ると昔の都電のレールを、大きな木の杭で塞いで、道を作っている所がある。そこまで来た時、彼女の目に一人の乞食が映った。乞食は、 年なんぞはまるっきり解らず、ただその太い木の杭にもたれかかり、坐っているだけだった。丁度彼女が乞食の前を通り過ぎる時、男とも女ともつかないその乞食と視線が合った。しかし、乞食はそのまま、彼女を通した遠くを視る目に変わっていた。彼女は歩く。こんな雨の中、なんであんな所に坐ってるんだろう。それっきりその乞食の事は忘れてしまった。その学生が住んでいる二階へ行くのには、一階の六坪ぐらいのバーの中を通らなければならない。そのバーは、ほとんどがライターとか放送関係とか、いわゆる日本の皮層文化をささえている人種が主な客であった。店にはまだ客はいなかった。ママ一人のこの店は、満員という事がなかった。ママは、突然現れた彼女に驚いた。「彼は?」「あの人今、捕まってんのよ」このママと彼は、彼女が同棲を始める前から、二階の二部屋で互いに行ったり来たりしていたらしい。しかし、彼女にはそんな事は、全然気にならなかった。「ああそう、またはいってんの」「今度は、随分長いのよ」酔うと、その昔中国で転々と渡り歩いて来たという話や、歌がただ一つの出し物のママは、少し淋しさを示した。「二階、開いてる」「ああ、開いてるよ」部屋は、カビ臭さと独り者の男の散らかし方で散乱としていた。長い事人が入った事がないとみえて部屋の中の空気は、今まで彼女が 歩いて来た空気と違う冷たさを持っていた。彼女は、敷っぱなしのカビ臭い蒲団にもぐり込むと、そのまま眠ってしまった。動きらしい動きもしないまま、二日も寝ていたろうか。体の神経がほとんど麻痺する位、体がゆるんでいた。そうした三日目の朝、彼は帰って来た。真暗な部屋の入口を、ガタンと音をさせたかと思うと、見覚えのある体が入って来た。彼は、部屋の中で一瞬戸惑いをみせたが、すぐ彼女を判別すると「なんだ、お前、帰ってたのか」。彼女は返事もせず、彼の動作を、もう一人の人間と自分が交す新しい空気の淀みを味わっていた。「今度は、やられたよ」「警察ってのは、病人を作る工場みてえだな」「今度ばかりは自分ってものを君じゃないけど考えさせられたよ」なんだか訳の解らな い事を、咳きながら、彼女が寝ている正反対の部屋の隅へ行って坐り込んだ。すぐにゴソゴソ這って来て、「タバコ、あるか」彼女、自分のバックを少し動かしてやる。タバコを取り出すと、また部屋のすみへ這って行って坐り込む。マッチの音がして、彼の顔が暗い中に浮び上がる。疲れているはずなのに、髭も伸びないで意外にシャンとした顔をしている。「きれいな顔してんのね」「警察も、最近は、出す時にゃちゃんと化粧させるんだ。ぶん殴った分だけ厚化粧させられるのさ」この小さなセクトを持っている学生は、その何十回目かの投獄の疲れの割には、自分の部屋に自分の女が待っていたという事で、単純に動物的な温かみを感じ、活発にしゃべり続けた。「今度は、黄色いフィルター早かったじゃないか」「向こうもこっちもなれあいさ、狂ってる事をお互いゲームにしちまってるのさ」「体は、元通りになってんのか」「うん、男と寝る事出来るよ」「奴等はよ、話で通じさせようとしないんだ。こっちの事、ガキの病気かママゴト位にしか考えていないんだ。奴等の話の原点は、結局暴力なんだ、人間の最も単純な所からの、発想なんだ。あいつらの錯覚ったらないぜ。それに、あいつ等の顔ときたら、ほとんど、パッケージに近いんだ。だから、話なんてものにまるでならない。猿同士が金使って、漫才やってるようなものだ」「私の方も、黄色い漫才ごっこだよ。ちょっと飽きて来たけどね」「お前はまとも、過ぎるんだよ。自分自身にさあ」「あんただってまともだよ。それも男の過剰なエネルギーって奴でさあ。人の事なんか放っとく方がいいよ」話が止切れて数分たった。「私、オナカすいたよ」「そうだな」入って来た時と同じ音をさせて彼は出て行った。どうやら、隣のママの部屋へ行ってるらしい。二言、三言、話し声がしてママの声とも、何んともつかないしゃべり声がする。「電気つけるぞ」入って来るなりそう言って、片手で天井のスイッチをひねる。もう片方の腕から、何やら音を立てて落ちる。「ああしまった!」明るくなった電灯の下で、丼から半分位こぼれかかった五目メシみたいなものがころがっていた。窓らしい窓のない部屋だから、昼でもアンダーな部屋の明るさがようやく適正になる。彼女もようやく起き上がり、二人でそのメシをモソモソ食べ出した。冷えて口にまずかったが、二 人には、久しぶりのメシらしいメシであった。食べ終って、彼はタバコを歯でくわえ、六十Wの電球を見つめ、くわえタバコを、親指と人差し指で根元から先へとしごいていた。その動作を彼女、三十分近くも見つめていた。小さな牢屋のような部屋の中は、二人の発するアクでほとんど完全な密室と化していた。
彼は、彼女の手を取って立ち上がらせると、肩の上から、抱き寄せて、暫くの間、じっと彼を見つめている彼女の目を、見つづけた。それは、冷たくて、やや、無に近い感じを、含んでいた。それから彼は、一層、彼女を、引き寄せ、自分に向かっている彼女の左側に頭を、持って行き、彼女の頭を、自分の右肩に引き寄せる。気持ちの良い沈黙が、続く。ジャニス・ジョプランのように、なりたいと彼女は思った。彼は、彼の腕を、彼女の前面にもって来ていた。とても、ゆっくりと、細いが確かな、豊かさを持って、彼女を、裸に誘って行く。「ああ、この人だった。やっぱり」裸になっていく、自分の体の冷たさとは、反対に、彼女は、自分が、熱くなって行くのを、確実に、感じていた。いつの間にか 、彼も全裸であった。立ったまま、二人はお互いの、ぬくもりが、完全に同じ温かさになるのを待った。彼女は、その時を、感じ取ると、垂直に、自分の体を下げて行った。丁度、ヘソの辺りで、彼女の舌は、活発に動き出していた。彼のヘソは、形のいい、品のある形と、凹みを持っていた。そのヘソを、触れるか、触れないほどの、微妙さを、持って彼女は、愛し込んでいった。ヘソの下の陰毛は、正に、彼女の舌を、より活発にさせる触発剤だった。彼の彼は、未だたれて、力を含んでいなかった。下からすくうように、彼女は、自分の口の中へ、入れて行く。彼の体に、ほんの少しの動揺が働く。彼の尻に、両手を廻し、彼と、彼の丸い二つの玉を、同時に、口に含んで、舌をゆるやかに、口の中でかき廻す 。しだいに、彼は、意思を、持ち始め、とても、彼も、玉も、一緒に、口に入れていられなくなり、その立ち出した彼と、玉を、交互になめまわす。彼自身が非常な脹らみと共に、血管が、二筋、三筋とはっきり浮き上って来る。彼は、優しく彼の手で、彼女にポイントを、与えると、ヒョイと、彼女を持ち上げて、三日かかって彼女が、温かくした万年蒲団に寝かせた。蒲団に、入っても、彼女は、自分から動いた。彼が、しっかり体の位置を、定めない内に、彼女の口は、彼を吸っていた。彼は、両手を、自分の頭にしいて、彼女のなすがままに、なっていた。舌は、モーターのような回転で、彼自身を回り彼を擁立させていった。その20数センチになった、彼自身を、彼の右足を抱えるように、彼女の左腕が、 抱え込み、手は、しっかり、そのモノを握り込んだ。空いた舌は、なおも欲望をつのり、後のもっと下へと、
 まさぐっていった。肛門の周りは、溢れ出る臭いと、汗で、じっとりとしていた。どんどん彼女は、なめる。そして、舌を槍のように、とがらせて、彼の尻の中へ、体ごとぶつけていった。「大丈夫か」「あなたのためなら、御手洗の始末だって平気よ」舌の先が、体の表面とは、違う、肉とも、何ともつかない彼の体の中側のタッチを、彼女に、伝えて来る。「こっちへ来いよ」そう言って、彼は、彼女の下半身を、強引に、自分の頭の方へ、引き寄せ、彼女を自分の頭の上にのせ、両手を、彼女の両方の膝の裏側へまわし、百パーセント彼女を、自分の顔の正面へ持って来る。そうして、下りて来る彼女 の液と、自分の唾が、自分の首辺りまで、べっとり濡らし、彼は、自分の後頭部が丁度、子供の時、氷を食べた時、痛くなるような痛みを憶えながら、彼女の穴へ向かって、舌をさし込み、クリトリスをしゃくる。そうした二人の出す汗と、液と、臭気の混濁の中で、彼女に小さいが、静かな波が、やって来るのを、彼女の体が教えていた。彼女は、再び、あの恐ろしいプラスとも、マイナスともつかない不安定な時が、やって来るのだと思った。彼は、何かお経でも、となえるようなリズムで、彼女を落して行く。それは、まるで、クシャミが、出るような感じで、彼女をおそった。「ああ!」「ああ!」「ああ」ほとんど、彼女は、自分自身が、無くなるような、心の震えを憶えた。が、次の瞬間、「ああまただ 」「ああまたこれだ」心は、再び、自分を取り戻し、体だけは、完全に、アクメ化していた。彼は、自分の股の辺りに、冷たい、汗でも、つばでもない、彼女の水が、したたり落ちて来るのを感じた。「駄目だったか」彼女は、答えない。パアッと横倒しに、彼の横へ、ころがり離れた。その顔にあるのは、涙だけだった。「しょうがないよお前」彼は何を言葉にしても意味と力を持たないのを承知でしゃべっていた。私は何故こうなんだ。いつも何故体だけ勝手に行っちまうんだ。彼だけが、100回やる内の一回位だけ、両方いかしてくれていた。しかしこの百分の一も、彼の人間から来る誠意がもたらしているもので、私は時々錯覚をしていただけとは違うだろうか。彼女は、頭だけが、ボーンと殴られたような判別のつかない冷たさで分離し、体だけが異常に高熱を伴っている自分を、再び記憶した。長い沈黙と静けさが続いた。幾本目かのタバコを吸い終る。「出ようか」「ウン」二人は、ゴソゴソ身じまいを始め、彼女は鏡を見ていた。鏡の中の顔が以前にも増して、陶器のような白さになって、もう少ししたら血管が出て来 そうな感じがして、身震いをした。下のバーは、軽薄文化のサービス人達でけっこう一杯になっていた。二人は時間が夜になっているのに初めて気付いた。知った顔とありもしないような挨拶を交し、ママは意味あり気な視線を二人に送って来る。二人の行為を知っていたのであろう。二人は、そんな事はなれっこだし、とんと気にならなかった。外は、相変らずの雨で凸凹の道がつやつやと光っていた。いつもは外に出て客を引いている、陽気でどこか線が一発抜けているような女達も、今日は店の奥に引込んでしまっているらしい。二人が入った中華メシ屋は、にんにくやにらの臭いがたちこめ、体と、はいているミニスカートのどちらが表面か解らないような配り女が、すごく派手な音を立てて、ガシャガシャ と食器を洗っている。調理台の上の煙抜きのための四角い漏斗をさかさにして、天井からぶら下げたようなその角に、ビニールの袋がくくりつけてあり、その中に、その漏斗からしたたり落ちて来た茶黒い油液がかなり貯っている。煙と湯気の立ちこめる中で、二人の男が立ち働いていた。二人は、長いカウンターを通りこして、奥の方には三つぐらいあるテーブルの一つに空席を見つけた。「新宿っての、何か、人間の動物園みてえだな」突然、彼が、しゃべり出した。「ちょっと前までは、俺には、ここが本当の、学校みてえな意味を、持っていたんだ。本当の学校の方が、トコロテンの機械みたいな感じで、俺は、トコロテンになって、食べられるのは、いやだったし、そんな時、ここは、いつも、俺の学校み たいだった。ちゃんとしたベースと、空気が、あったんだ。ここには・・・。しかし、最近は、ここも、ただの動物園の檻に、見えて来ちまったんだ」暫く空白が続いて、彼女がぽつんと、「新宿は、東京のオ××コさ」彼は彼女の口元に目をやりながら、「じゃ、東京は?」「東京は日本のオ××コさ」「じゃ、日本は、地球の大陰部って訳だ」後は黙りこくってモクモクと食べ続けた。彼女は、バーの二階へもどるべく雨の中を歩いていた。彼は、話し合いがあるとかで、中華メシ屋を出た所で別れた。その走り去る男のモーションを見ながら、他人じゃあいつが一番近いなと、かすかなぬくもりが自分の中にあるのを感じた。この間の乞食が、同じ場所でうずくまっている。店の中は彼女が初めて見るぐらいのこみようだった。まるで満員電車の中だった。人をかきわけて、奥の階段の近くまで、来た時だった。「やあ」聞き憶えのあるフレーズと音域で、彼女を一人の男が呼び止めた。その男は、広告代理店のややエリート寄りの、彼女と前に二、三回寝た事のある男だった。この賑やか過ぎるうるささには閉口だったが、何か水の流れのように、その男の前で彼女は立ち止った。酒を飲んでもいいなと思った。「ママ、酒」彼女は呶った。それ位にしないと通じない。彼女の前の男はかなり飲んでいたが、この男のとりえのひとつに、飲んでもどこか覚めてる所があって、酔っても酔っぱらうという事はなかった。「広告は、どう?」彼女は下らない会話を向ける。「変わらないねえ」「何故、いつまで、やってんの」「そ れが、俺の生きてる証拠さ」胴でもいい会話が続き、彼女も何杯目かの酒を口にしていた。二人が立っている場所は、トイレのすぐ近くで、トイレに行く男たちが通る度に二人は体をよじらせた。店は、益々混んできて、タバコの煙としゃべり声と有線放送で、映画に出て来るカスバかなんかの地下の飲み屋みたいな様子を、呈していた。
まさぐっていった。肛門の周りは、溢れ出る臭いと、汗で、じっとりとしていた。どんどん彼女は、なめる。そして、舌を槍のように、とがらせて、彼の尻の中へ、体ごとぶつけていった。「大丈夫か」「あなたのためなら、御手洗の始末だって平気よ」舌の先が、体の表面とは、違う、肉とも、何ともつかない彼の体の中側のタッチを、彼女に、伝えて来る。「こっちへ来いよ」そう言って、彼は、彼女の下半身を、強引に、自分の頭の方へ、引き寄せ、彼女を自分の頭の上にのせ、両手を、彼女の両方の膝の裏側へまわし、百パーセント彼女を、自分の顔の正面へ持って来る。そうして、下りて来る彼女 の液と、自分の唾が、自分の首辺りまで、べっとり濡らし、彼は、自分の後頭部が丁度、子供の時、氷を食べた時、痛くなるような痛みを憶えながら、彼女の穴へ向かって、舌をさし込み、クリトリスをしゃくる。そうした二人の出す汗と、液と、臭気の混濁の中で、彼女に小さいが、静かな波が、やって来るのを、彼女の体が教えていた。彼女は、再び、あの恐ろしいプラスとも、マイナスともつかない不安定な時が、やって来るのだと思った。彼は、何かお経でも、となえるようなリズムで、彼女を落して行く。それは、まるで、クシャミが、出るような感じで、彼女をおそった。「ああ!」「ああ!」「ああ」ほとんど、彼女は、自分自身が、無くなるような、心の震えを憶えた。が、次の瞬間、「ああまただ 」「ああまたこれだ」心は、再び、自分を取り戻し、体だけは、完全に、アクメ化していた。彼は、自分の股の辺りに、冷たい、汗でも、つばでもない、彼女の水が、したたり落ちて来るのを感じた。「駄目だったか」彼女は、答えない。パアッと横倒しに、彼の横へ、ころがり離れた。その顔にあるのは、涙だけだった。「しょうがないよお前」彼は何を言葉にしても意味と力を持たないのを承知でしゃべっていた。私は何故こうなんだ。いつも何故体だけ勝手に行っちまうんだ。彼だけが、100回やる内の一回位だけ、両方いかしてくれていた。しかしこの百分の一も、彼の人間から来る誠意がもたらしているもので、私は時々錯覚をしていただけとは違うだろうか。彼女は、頭だけが、ボーンと殴られたような判別のつかない冷たさで分離し、体だけが異常に高熱を伴っている自分を、再び記憶した。長い沈黙と静けさが続いた。幾本目かのタバコを吸い終る。「出ようか」「ウン」二人は、ゴソゴソ身じまいを始め、彼女は鏡を見ていた。鏡の中の顔が以前にも増して、陶器のような白さになって、もう少ししたら血管が出て来 そうな感じがして、身震いをした。下のバーは、軽薄文化のサービス人達でけっこう一杯になっていた。二人は時間が夜になっているのに初めて気付いた。知った顔とありもしないような挨拶を交し、ママは意味あり気な視線を二人に送って来る。二人の行為を知っていたのであろう。二人は、そんな事はなれっこだし、とんと気にならなかった。外は、相変らずの雨で凸凹の道がつやつやと光っていた。いつもは外に出て客を引いている、陽気でどこか線が一発抜けているような女達も、今日は店の奥に引込んでしまっているらしい。二人が入った中華メシ屋は、にんにくやにらの臭いがたちこめ、体と、はいているミニスカートのどちらが表面か解らないような配り女が、すごく派手な音を立てて、ガシャガシャ と食器を洗っている。調理台の上の煙抜きのための四角い漏斗をさかさにして、天井からぶら下げたようなその角に、ビニールの袋がくくりつけてあり、その中に、その漏斗からしたたり落ちて来た茶黒い油液がかなり貯っている。煙と湯気の立ちこめる中で、二人の男が立ち働いていた。二人は、長いカウンターを通りこして、奥の方には三つぐらいあるテーブルの一つに空席を見つけた。「新宿っての、何か、人間の動物園みてえだな」突然、彼が、しゃべり出した。「ちょっと前までは、俺には、ここが本当の、学校みてえな意味を、持っていたんだ。本当の学校の方が、トコロテンの機械みたいな感じで、俺は、トコロテンになって、食べられるのは、いやだったし、そんな時、ここは、いつも、俺の学校み たいだった。ちゃんとしたベースと、空気が、あったんだ。ここには・・・。しかし、最近は、ここも、ただの動物園の檻に、見えて来ちまったんだ」暫く空白が続いて、彼女がぽつんと、「新宿は、東京のオ××コさ」彼は彼女の口元に目をやりながら、「じゃ、東京は?」「東京は日本のオ××コさ」「じゃ、日本は、地球の大陰部って訳だ」後は黙りこくってモクモクと食べ続けた。彼女は、バーの二階へもどるべく雨の中を歩いていた。彼は、話し合いがあるとかで、中華メシ屋を出た所で別れた。その走り去る男のモーションを見ながら、他人じゃあいつが一番近いなと、かすかなぬくもりが自分の中にあるのを感じた。この間の乞食が、同じ場所でうずくまっている。店の中は彼女が初めて見るぐらいのこみようだった。まるで満員電車の中だった。人をかきわけて、奥の階段の近くまで、来た時だった。「やあ」聞き憶えのあるフレーズと音域で、彼女を一人の男が呼び止めた。その男は、広告代理店のややエリート寄りの、彼女と前に二、三回寝た事のある男だった。この賑やか過ぎるうるささには閉口だったが、何か水の流れのように、その男の前で彼女は立ち止った。酒を飲んでもいいなと思った。「ママ、酒」彼女は呶った。それ位にしないと通じない。彼女の前の男はかなり飲んでいたが、この男のとりえのひとつに、飲んでもどこか覚めてる所があって、酔っても酔っぱらうという事はなかった。「広告は、どう?」彼女は下らない会話を向ける。「変わらないねえ」「何故、いつまで、やってんの」「そ れが、俺の生きてる証拠さ」胴でもいい会話が続き、彼女も何杯目かの酒を口にしていた。二人が立っている場所は、トイレのすぐ近くで、トイレに行く男たちが通る度に二人は体をよじらせた。店は、益々混んできて、タバコの煙としゃべり声と有線放送で、映画に出て来るカスバかなんかの地下の飲み屋みたいな様子を、呈していた。
さっきから、男は彼女のミニの横のチャックを、少しずらし、そこから、手を入れ、彼女のあそこを、揉みほぐすように、愛撫していた。男は、リズムを取って、かなり彼女を、いい気分にさせていた。彼女が、波の上のあたりに、登ると、ゴツンと、トイレに、いく人が、通り、その都度、彼女が、白けた。男は、酒場全体を、感じ取り、その中で、全く秘密裏に、自分の前の女に、繰り返し、繰り返し、反復を、続けて行く。この男は、昔、ベットの中で、よくしゃべり、自分の広告の事を、資本の金もうけだけの、エゴイズムと、大衆の、商品に、対する、目の甘さや、産業に対する盲から来る、大衆自身のエゴイズム、この両方のエゴの、ぶつかりから来る矛盾を、ちゃんと見分けて、俺は、どっちの 側にも、つかないで、両方を、見すえて、錯覚のない広告ってのを、作ってやるんだ、と息まいていた事があった。それが、今は、一体、どうなってんだろう。と男は、ほとんど、さっきから、二人の前どうし、くっついている体の自分の前の、チャックを、下し出した。右手のグラスは、そのままである。男の左手は、一分の無駄もなく、すでに、拡張しきっている。自分自身を、彼女のスカートの下から、奮うように突き上げて来た。彼女の濡れた入口で、ほんの、二、三回探したかと、思うと、そいつは、確かな、堅さと、逞しさを持って、彼女の中へ、ぬらりと、入って来た。彼女は、自分の持っているグラスの内側に、押し付けられる、自分の手の指間が、より強く、はっきりと、滑り込んで来るのを、見 ていた。そして、男に向って、グイと、自分の腰を、しゃくり上げてやった。そんな二人を、周りは、全く、気付かなかった。皆んな、自分のことを、しゃべり続ける事に、全てのエネルギーを、使っているかのようだった。廻り切っている酒と、人いきれと、二人自身が、出す摩擦で、彼女は、クラクラするような、まるで麻薬をやっているような、高温な、味わいを、吸い取っていた。そういえば、この男は、以前に、マリファナを、吸わせて、ボリューム一ぱいの、マクドナルド&ジャイルスを、ヘッドホーンに流し、その私に、強烈なインサートを、繰り返した事が、あった。しかし、彼女は、あの時よりも、この周りに、人がいっぱいのこの雰囲気のほうが、よりエキサイトした。「貴方ナイフみたいよ」 彼女がいい終わらないうちに男の表情が、笑うような、しかめっ面を、したかと思うと、彼女に、はめていなかったら、一メートル以上も、飛んでるだろう、それ程の勢いで始まった。男の頂点は、彼女の下後部、それも腹の中を、熱い、大きな沼として行った。終りながら、彼女は、こういった相も変らぬやり方、入れたり、抜いたりするSEXに、いや気がしていた。これでは、私は、もう駄目なんだ。男のモノが、自分の中に、入っては出る肉の交りには、俗にいう不感症とは違う何か拒絶反応が、やる度に、起こって来るのを、堪えることが、出来なかった。「飲みに行こうか」今も飲んでるくせに、男はそう言った。「いいよ」答えると、彼女は自分から動き出していた。外へ出ると、雨は小降りになって、薄 いレースが降りてくるように細い雨がしょぼふっていた。男と肩を並べて歩きながら、数度身震いした。「どこへ行く」「うん」その時、ギターを持った小肥りした人影が二人を横ぎる。「あ、帰ってたんか」その男は、モトロフとかなんとかいう、ロシアの政治家のアダ名の中年の流しだった。彼は、自分が歌えばかなり上手く歌うのに、客に歌わせるのが好きで、常に歌わせ上手だった。その流しは、いつも五冊位の手帳に色色な戦前戦中戦後の歌をいっぱい切り抜いて貼りつけ、自分でも書きつけたりしていた。その歌詩カードを、客に向ってページを開いては渡しながら、次々に歌わせて行くのだった。彼女は、その流しの、いつも無表情なのが好きで、十回に一回ぐらいは歌う事もあった。「ウン、ちょっ と前にね」「そうか」そういってその流しは勝手に納得して行き過ぎていってしまった。彼女は、そういうギター弾きの、何かまとまらない中途半端さが好きだった。例の都電の、廃止になったレールの所まで来ると、あの乞食は相変らずいた。今度は、立ち上って一本の杭に、どこか体でも悪そうな恰好で寄りかかっていた。彼女には、その寄りかかり方にひどく、後髪を引かれる思いで、通り過ぎていった。その広告屋の連れて行った店は、出来たのが新しいらしく、妙に店構えが浮き立っていた。この店をデザインしたデザイナーは、ここを電車かバスの中みたいにしたかったらしく、長細いカウンターの横に互いに向い合った、まるで電車の二人ずつ坐って向き合う恰好になっていた。その間にテーブルがあ る。いやに窮屈だが、店のスペースの割には、数がさばけてる具合だった。店の客は、若い学生かそれに近い人種がほとんどだった。店はいっぱいで、丁度中頃のボックスが、片側だけ空いていた。そこへ、彼女から先にすべり込み―足を折って文字通り横になってすべり込む。坐って一息ついて前を見る。年の頃は十五、六位にしかみえない男と女が、両方が肘をついてこっちの事なんか全く気にしないで、顔を見合って口だけが達者に動き、何やら話し合っている。二人とも、ウイスキーのストレートって感じで、やっていた。彼女は男に「あんたここはよく来るの」「そうでもないんだけどここは若い奴が多くていいんだ」ここへ来たら自分のエネルギーが若さを持つんだ、というようないい方をして、何か飲 む酒を、カウンターの方へ向ってしゃべっていた。広告屋と同年輩のバーテンは、男に向って二言三言何かをいってよこし、男もそれに多少周りを意識した感じで元気っぽく答えていた。「最近、貴方のいう景気って奴はどうなの」「悪くはないんだが、金の行き所が片よってこちとらはやっと明日が来てるって、とこだなあ」「女房はどうしてんの」「ああ元気だよ」この男は、昔に女房と別れ話をやってかなり成立したかにみえたが、最後の最後に、女房が子供を作ってしまって、どうしても生むといって、そういった女の最悪の手に引っかかって、今だにこの男はにえ切らない面を持っていた。しかし、彼女はこういったこの男のどちらにもなり切れない所を好きだった。男なんて、このぐらいがいいと思って いた。いっぱい目のウイスキーを、口にした時、突然、さっきの乞食の事が頭に浮んで来た。ただ、それだけだった。小一時間もいただろうか。広告屋は、奥のトイレに行った帰りに、顔見知りの男と、かれこれ二十分近く立ったままで話し続けている。相変らず活発に飲み、しゃべり続ける前の二人と、遠くにいる広告屋と煙でぼんやりと霧がかかったような店を見て、ひどくけだるさを感じ、出よう、そう思うともう体は動き出した。彼女が去ったのをほとんど誰も気が付かなかった。乞食は、先程の杭にまだ寄りかかっていた。彼女は、どうにも簡単に通り過ぎる事が出来ず、何か、えもいわれぬ電波に引っぱられるように、全く自分の意識の外で、知らぬ間にその乞食の肩に手をかけていた。乞食は、何んの 反応もしない。かけている手を数回彼女は揺すった。「すみません」いやにか細く、デリカシーを含んだ声がした。乞食の口から発した声でなく乞食の体全体から出て来るようであった。「どうした?」「・・・・」「どこか、調子悪いの?」「・・・・」「ハラでも、減ってんの」「・・・・」暫くの沈黙があり、「あっちへ、行ってくれ」と乞食がいう。「どっか悪いみたいだよ。それとも、あんた、酔っぱらってるの」「酒なんか飲まない。いいから、あっちへ、行ってくれ」「私、あんたの事、気になるよ」突然、乞食はもたれかかって来た。彼女は驚いて退ずさりしようとしたがおそかった。乞食の表現のしようのない臭気と膚ざわりが伝わって来る。乞食の足は、形こそしっかりしているが、ほとんど歩く力はないようだった。「連れてってくれ」「どこへ」「ちょっと先だ」彼女は、覚悟を決め、そんなに大きくなくどちらかと言うと彼女より小がらな乞食を背中にしょった。その異常な軽さに驚き、この乞食は一体男なんだろうか、それとも女なんだろうかと、背中からの伝わりを感じ取ろうとした。しかし、解らない。まるで軟体動物を背おっているようだった。乞食は、失くなった都電のレール添いに、かなり暗く木造の建物の裏側が並ぶ線路に面した一角へ導いていった。そして、そこだけコンクリートの建物で、天井が抜けてしまったような、建築を途中でストップして相当時がたっている建物の地下へ、蟻が巣にもぐり込むようなモーションで入り込んで行く。彼女も、同じモーションを繰り返し、穴へ入って行く。そこは、生き物が腐って、それを全部集めたような、嗅覚の限界を越えた臭を、放っていた。彼女は、今まで経験した事がないような世界へ入り込んだ気がして、必死に、自分をコントロールしていた。真暗でも乞食は、目が、見えるらしく、木造の人影が動くように彼女に寄って来る。そうして、まるで、獣が獲物を自分で巣へはこび込んで、それを食いあさるが如く、彼女の腕と言わず、足といわず、なめ廻し出した。
一時間近くも、乞食は、そうしたなめ廻しを、続ける。すでに、彼女は、全裸になっていた。彼女も、乞食の発する臭と、そのまるで、人間ばなれした肌ざわりにも、馴れ出して、その男女の区別のつかない乞食の股のあたりを、乞食が、体の位置を、変える度に、アプローチを、始めていた。彼女の手に、伝わって来る感触は、かなり異常な物だった。男のモノが、あるくせに、その下方に、まるで、女と同じような、湿った穴があった。
 そのくせ、睾丸は、まるで、なかった。彼女は、そういった現実も、入り交って、仲々、SEXという気分には、なれなかった。一時間半も、たったろうか、彼女の体は、乞食の舌で、全身濡れていた。そして、彼女の体が、驚異からようやく遠のき、肉体自身が、一種の麻 痺を、始めているのを、憶えた。それからだった。乞食の異様な行為が、始まったのは。彼女の足を、いっぱい広げると、彼女の両足と、脇を、かかえ込み、丁度、彼女の部分が、乞食のヘソの辺りまで、彼女の腰を、引き上げたその時になって初めて、彼女は、乞食が、かなり特殊なヘソを、しているのに、気が付いた。乞食は、そのヘソを、彼女のクリトリスへ持って行き、ゆるやかな動きを、始める。今までのどの男の指や、舌、それに、どの女のゴールドフィンガーも、舌も、ほとんど上物といわれるのは、全て知っている彼女であるが、この形容しがたい、柔らかさと、芯をもった物体が、自分のクリトリスを上下すると、その過去の美の全てを、越えていくのを、明確に、彼女の体は、表わしていた。この女は、今まで、肉の交わりで、声というのを、出した事が、かつて、なかった。それが、声とも、唸りともつかない発声を断続的に、発し始めていた。彼女は、段々いつもとは違う、内面のうねりを、見付け出していた。「ああ、なんだか違う」「自分が」「涙が出るみたいだ」訳のわからぬ言葉が自分の中から突き上って来る。なおも、その長さも、太さも解らないヘソは、彼女をどこかへ走らせる。溢れ出る汗と、強くつむり過ぎた目から、出て来る涙、それが、ポトポト音を立てて、体から離れて行くのが、わかった。得体の知れないそれは、彼女のクリトリスを、愛撫しながら、その先端が、彼女のハラの中へと、まるで、それ自身が、コントロール出来るが如く、入って来た。「ああ、さわる」その先端部は、ハラの中の感度を、全部、読み取っているが如く、まるで、蛇のように、くねくねと、彼女の中を、うねる。そのかつてなかった作用力に、彼女は、自分の全てのわだかまりが、失くなっていくのを、感じ、「ああ、これだ」「自分が、無くなる」「私なんて、初めから、無かったんだ」「私が勝手に、意識してただけなんだ」「ああ、豊か」「ああ、何も、見えなくなって来た」「ああ、何も、輪郭が、なくなっていく」本当に細胞という細胞が、見事に、遠く、消えていくようだった。「ギャア!」建物が、その声で、数条の、ひび割れを、したが如く、鮮烈な声を、彼女は、上げた、そして、すこし、間をおいて、「キレイ!」それは、まるで、子供の声のような、どんな音楽も、それに、優る事の、出来ないような、美しい、響きを、持った、小さな、声だった。正に、豊かさと、優しさ、だけが、彼女を、支配、していた。その瞬間、彼女の、右手が、左手首の、5本の、傷を、斜めに、横切る、よう・に・走・っ・た。
そのくせ、睾丸は、まるで、なかった。彼女は、そういった現実も、入り交って、仲々、SEXという気分には、なれなかった。一時間半も、たったろうか、彼女の体は、乞食の舌で、全身濡れていた。そして、彼女の体が、驚異からようやく遠のき、肉体自身が、一種の麻 痺を、始めているのを、憶えた。それからだった。乞食の異様な行為が、始まったのは。彼女の足を、いっぱい広げると、彼女の両足と、脇を、かかえ込み、丁度、彼女の部分が、乞食のヘソの辺りまで、彼女の腰を、引き上げたその時になって初めて、彼女は、乞食が、かなり特殊なヘソを、しているのに、気が付いた。乞食は、そのヘソを、彼女のクリトリスへ持って行き、ゆるやかな動きを、始める。今までのどの男の指や、舌、それに、どの女のゴールドフィンガーも、舌も、ほとんど上物といわれるのは、全て知っている彼女であるが、この形容しがたい、柔らかさと、芯をもった物体が、自分のクリトリスを上下すると、その過去の美の全てを、越えていくのを、明確に、彼女の体は、表わしていた。この女は、今まで、肉の交わりで、声というのを、出した事が、かつて、なかった。それが、声とも、唸りともつかない発声を断続的に、発し始めていた。彼女は、段々いつもとは違う、内面のうねりを、見付け出していた。「ああ、なんだか違う」「自分が」「涙が出るみたいだ」訳のわからぬ言葉が自分の中から突き上って来る。なおも、その長さも、太さも解らないヘソは、彼女をどこかへ走らせる。溢れ出る汗と、強くつむり過ぎた目から、出て来る涙、それが、ポトポト音を立てて、体から離れて行くのが、わかった。得体の知れないそれは、彼女のクリトリスを、愛撫しながら、その先端が、彼女のハラの中へと、まるで、それ自身が、コントロール出来るが如く、入って来た。「ああ、さわる」その先端部は、ハラの中の感度を、全部、読み取っているが如く、まるで、蛇のように、くねくねと、彼女の中を、うねる。そのかつてなかった作用力に、彼女は、自分の全てのわだかまりが、失くなっていくのを、感じ、「ああ、これだ」「自分が、無くなる」「私なんて、初めから、無かったんだ」「私が勝手に、意識してただけなんだ」「ああ、豊か」「ああ、何も、見えなくなって来た」「ああ、何も、輪郭が、なくなっていく」本当に細胞という細胞が、見事に、遠く、消えていくようだった。「ギャア!」建物が、その声で、数条の、ひび割れを、したが如く、鮮烈な声を、彼女は、上げた、そして、すこし、間をおいて、「キレイ!」それは、まるで、子供の声のような、どんな音楽も、それに、優る事の、出来ないような、美しい、響きを、持った、小さな、声だった。正に、豊かさと、優しさ、だけが、彼女を、支配、していた。その瞬間、彼女の、右手が、左手首の、5本の、傷を、斜めに、横切る、よう・に・走・っ・た。